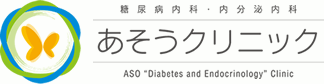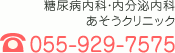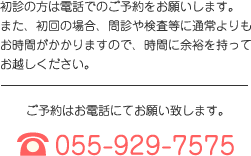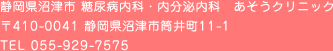花水木の会 第12回 「低カロリーの甘味料を使ったお菓子を作ろう」
第12回花水木の会では調理実習を行いました。
低カロリーの甘味料を使い、カップサイズのシフォンケーキを作りました。



和気あいあいとした雰囲気の中、作ったケーキはふっくら焼きあがりました。
甘味料を使ったとは思えず美味しかったです、と好評いただきました。
低カロリーの甘味料を使い、カップサイズのシフォンケーキを作りました。
和気あいあいとした雰囲気の中、作ったケーキはふっくら焼きあがりました。
甘味料を使ったとは思えず美味しかったです、と好評いただきました。
平成27年7月のひとこと:糖尿病神経障害③
みなさんこんにちは!梅雨の時期もそろそろ終わり、本格的な夏になりますね。
この時期は熱中症に気をつけてください。ただ、脱水を心配してスポーツ飲料や
ジュースをたくさん摂ることはやめましょう
さて今月は、先月予告した通り血管年齢や動脈硬化の進行の程度、神経障害を調べる
検査についてご説明します。
①神経伝達速度検査(NCV)・・・検査科の検査技師が行います。
神経伝導速度検査とは、糖尿病3大合併症の1つである「糖尿病性神経障害」を見つける
ための検査です。
手足の運動神経・感覚神経に与えた刺激が神経内に伝わる速度を測定し、手足の神経に
障害がないかどうかをみる検査です。障害がある場合は伝導速度が低下していきます。
神経障害は末梢から進行していくため、上肢・下肢の4神経で検査を行います。
糖尿病の場合は下肢の伝導速度から低下していきます。
②動脈硬化検査(ABI、PWV)・・・看護師が行います。
血糖が高値の状態が続き血管がダメージを負いつづけると血管が硬くなる動脈硬化が
起こります。動脈硬化が起こると心疾患や脳血管疾患にかかるリスクがとても高くなります。
動脈硬化検査は、現在動脈硬化がないか、血管が詰まっていないかを
調べる検査です。
★ABI(血管のつまり具合)
足首と上腕の血圧の比を測定することで血管のつまり具合がわかります。
★PWV(血管年齢)
心臓から押し出された血液により生じた拍動が、血管を通じて手や足に届くまでの速度を測ることで血管年齢を調べます。
血管のしなやかさが失われると血管年齢が高くなります。
糖尿病になってから期間が長い、もしくは血糖が高い状態が続いており足の痛みがある方は一度検査を受けることをお勧めします。
検査をご希望の方は、医師または看護師にご相談ください。
この時期は熱中症に気をつけてください。ただ、脱水を心配してスポーツ飲料や
ジュースをたくさん摂ることはやめましょう
さて今月は、先月予告した通り血管年齢や動脈硬化の進行の程度、神経障害を調べる
検査についてご説明します。
①神経伝達速度検査(NCV)・・・検査科の検査技師が行います。
神経伝導速度検査とは、糖尿病3大合併症の1つである「糖尿病性神経障害」を見つける
ための検査です。
手足の運動神経・感覚神経に与えた刺激が神経内に伝わる速度を測定し、手足の神経に
障害がないかどうかをみる検査です。障害がある場合は伝導速度が低下していきます。
神経障害は末梢から進行していくため、上肢・下肢の4神経で検査を行います。
糖尿病の場合は下肢の伝導速度から低下していきます。
②動脈硬化検査(ABI、PWV)・・・看護師が行います。
血糖が高値の状態が続き血管がダメージを負いつづけると血管が硬くなる動脈硬化が
起こります。動脈硬化が起こると心疾患や脳血管疾患にかかるリスクがとても高くなります。
動脈硬化検査は、現在動脈硬化がないか、血管が詰まっていないかを
調べる検査です。
★ABI(血管のつまり具合)
足首と上腕の血圧の比を測定することで血管のつまり具合がわかります。
★PWV(血管年齢)
心臓から押し出された血液により生じた拍動が、血管を通じて手や足に届くまでの速度を測ることで血管年齢を調べます。
血管のしなやかさが失われると血管年齢が高くなります。
糖尿病になってから期間が長い、もしくは血糖が高い状態が続いており足の痛みがある方は一度検査を受けることをお勧めします。
検査をご希望の方は、医師または看護師にご相談ください。
平成27年6月のひとこと:糖尿病神経障害について②
みなさんこんにちは。
今月は、先月にひきつづき糖尿病性神経障害について、当院で行っている問診、
検査をどの様に行っているかご説明したいと思います。
まず自覚症状の問診をさせて頂きます。
糖尿病性神経障害の場合に出やすい痛みの状態や程度(焼けるような痛み、刺すような痛み、または足の裏で砂利を踏んでいる、または足の裏に紙が貼りついているような違和感があるなど)をお聞きします。
糖尿病性神経障害の症状は必ず左右対称に出現し、かつ足から起こることが多いため、症状の出現の経緯についてもお聞きします。またしびれやこむら返りを合併することもあるため、一見神経障害と関係のないような症状についてもお聞きすることがあります。
次に足の状態を診察します。
神経障害が進むと感覚が鈍くなり、怪我をして傷が出来たり、湯たんぽやあんか等で低温やけどをしても、気づかないことが多く、そのままにしておいて、足の壊疽などを起こしてしまうことがあります。その際、足に水虫などの感染がある状態だと、より足壊疽などの危険性が高いことが知られています。
そのため、水虫(趾間や爪)、巻き爪、潰瘍や傷の有無をしっかり確認することが大事です。さらに、足の血流が悪くなっているとより危険性が増すため、足の甲の動脈がしっかり触知できるかどうか、足趾や関節の色の変化などがないかを診察して確認していきます。
最後に専用の器機を用い検査を行います。
①アキレス腱反射:壁に手をかけてベッドの上で膝立ちをしてもらい、アキレス腱部をハンマー(打腱器)で軽く叩き、反射が正常かを検査します。
②振動覚:専用の音叉を用い、音叉の振動を感じる時間の長さを調べることで、振動を感じる神経(深部感覚)が障害を受けていないかを検査します。
③タッチテスト:細いナイロン線を足に押し付けて、触られたり圧を感じたりする感覚(圧触覚)の低下がないかを検査します。
④痛覚:竹串を用い、足の裏や甲を刺激して痛覚の低下を検査します。
次回は血管年齢や動脈硬化の状態や神経の伝達速度などを調べる検査について
ご説明します。
今月は、先月にひきつづき糖尿病性神経障害について、当院で行っている問診、
検査をどの様に行っているかご説明したいと思います。
まず自覚症状の問診をさせて頂きます。
糖尿病性神経障害の場合に出やすい痛みの状態や程度(焼けるような痛み、刺すような痛み、または足の裏で砂利を踏んでいる、または足の裏に紙が貼りついているような違和感があるなど)をお聞きします。
糖尿病性神経障害の症状は必ず左右対称に出現し、かつ足から起こることが多いため、症状の出現の経緯についてもお聞きします。またしびれやこむら返りを合併することもあるため、一見神経障害と関係のないような症状についてもお聞きすることがあります。
次に足の状態を診察します。
神経障害が進むと感覚が鈍くなり、怪我をして傷が出来たり、湯たんぽやあんか等で低温やけどをしても、気づかないことが多く、そのままにしておいて、足の壊疽などを起こしてしまうことがあります。その際、足に水虫などの感染がある状態だと、より足壊疽などの危険性が高いことが知られています。
そのため、水虫(趾間や爪)、巻き爪、潰瘍や傷の有無をしっかり確認することが大事です。さらに、足の血流が悪くなっているとより危険性が増すため、足の甲の動脈がしっかり触知できるかどうか、足趾や関節の色の変化などがないかを診察して確認していきます。
最後に専用の器機を用い検査を行います。
①アキレス腱反射:壁に手をかけてベッドの上で膝立ちをしてもらい、アキレス腱部をハンマー(打腱器)で軽く叩き、反射が正常かを検査します。
②振動覚:専用の音叉を用い、音叉の振動を感じる時間の長さを調べることで、振動を感じる神経(深部感覚)が障害を受けていないかを検査します。
③タッチテスト:細いナイロン線を足に押し付けて、触られたり圧を感じたりする感覚(圧触覚)の低下がないかを検査します。
④痛覚:竹串を用い、足の裏や甲を刺激して痛覚の低下を検査します。
次回は血管年齢や動脈硬化の状態や神経の伝達速度などを調べる検査について
ご説明します。