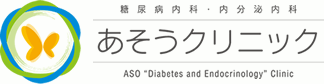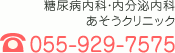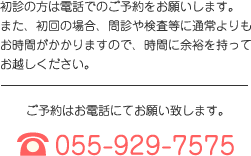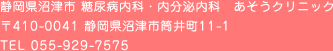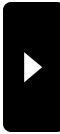令和7年4月のひとこと:糖尿病と睡眠時無呼吸症候群
みなさんこんにちは!
新年度が始まり暖かい日が増えてきましたね。
さて今月は、糖尿病と睡眠時無呼吸症候群についてお話ししたいと思います。
みなさんは
睡眠時無呼吸症候群(以下SAS=Sleep Apnea Syndrome)
をご存じでしょうか?
睡眠中に気道が一時的に閉鎖し、呼吸が止まる状態が繰り返される疾患のことを言います。
主な症状としてはいびき、睡眠中に呼吸が止まる、息苦しさを感じる、せき込むなどがあります。
そのような状態が続くと、睡眠の質が低下し日中に強い眠気を感じたり、頭痛や倦怠感、集中力の低下など、日常生活に支障が出てきます。中には、日中車の運転中に居眠りをしてしまい、死亡事故などの原因となることもあります。また、それだけではなく、心血管疾患や脳卒中などの死亡率の高い疾患の発症にもつながります。
実はこのSAS、糖尿病と深い関わりがあります。
まず、SASを患っていると、SASがない人に比べて糖尿病になるリスクが高いと言われています。
また、糖尿病の方の中にもSASを有病している方の割合は糖尿病のない方に比べて高いことが分かっています。
2型糖尿病の発症原因として、生活習慣の乱れがあげられます。食生活の乱れだけではなく、睡眠の質の低下により交感神経が活性化したり、ストレスホルモンが多くなり、血糖値や血圧が上昇したり、睡眠中に分泌される成長ホルモンの低下により脂肪が蓄積されやすい状態になります。
それにより肥満により首やあごに脂肪がつきやすくなり、それがSASの原因となります。
つまり、糖尿病と睡眠時無呼吸症候群はお互いの相互作用によって合併しやすく症状がさらに悪化することもあるため注意が必要です。
しかしSASの主な症状とされるいびきや無呼吸は本人が気づくことが出来ないため、家族やパートナーからの指摘で気づくことが多いです。
当院ではSASの簡易検査を行っています。
ご自宅に検査キットが送られてきて、一晩装着して返送していただくだけで検査結果が判明し、後日当院で結果の説明となります。
そのため、家族やパートナーの方からいびきや無呼吸を指摘されたことがある、日中の眠気が気になるなどの症状があれば当院の担当医師または看護師へご相談ください。
新年度が始まり暖かい日が増えてきましたね。
さて今月は、糖尿病と睡眠時無呼吸症候群についてお話ししたいと思います。
みなさんは
睡眠時無呼吸症候群(以下SAS=Sleep Apnea Syndrome)
をご存じでしょうか?
睡眠中に気道が一時的に閉鎖し、呼吸が止まる状態が繰り返される疾患のことを言います。
主な症状としてはいびき、睡眠中に呼吸が止まる、息苦しさを感じる、せき込むなどがあります。
そのような状態が続くと、睡眠の質が低下し日中に強い眠気を感じたり、頭痛や倦怠感、集中力の低下など、日常生活に支障が出てきます。中には、日中車の運転中に居眠りをしてしまい、死亡事故などの原因となることもあります。また、それだけではなく、心血管疾患や脳卒中などの死亡率の高い疾患の発症にもつながります。
実はこのSAS、糖尿病と深い関わりがあります。
まず、SASを患っていると、SASがない人に比べて糖尿病になるリスクが高いと言われています。
また、糖尿病の方の中にもSASを有病している方の割合は糖尿病のない方に比べて高いことが分かっています。
2型糖尿病の発症原因として、生活習慣の乱れがあげられます。食生活の乱れだけではなく、睡眠の質の低下により交感神経が活性化したり、ストレスホルモンが多くなり、血糖値や血圧が上昇したり、睡眠中に分泌される成長ホルモンの低下により脂肪が蓄積されやすい状態になります。
それにより肥満により首やあごに脂肪がつきやすくなり、それがSASの原因となります。
つまり、糖尿病と睡眠時無呼吸症候群はお互いの相互作用によって合併しやすく症状がさらに悪化することもあるため注意が必要です。
しかしSASの主な症状とされるいびきや無呼吸は本人が気づくことが出来ないため、家族やパートナーからの指摘で気づくことが多いです。
当院ではSASの簡易検査を行っています。
ご自宅に検査キットが送られてきて、一晩装着して返送していただくだけで検査結果が判明し、後日当院で結果の説明となります。
そのため、家族やパートナーの方からいびきや無呼吸を指摘されたことがある、日中の眠気が気になるなどの症状があれば当院の担当医師または看護師へご相談ください。
令和7年3月のひとこと:睡眠の大切さ・重要性
みなさんこんにちは、春の暖かさを少しずつ感じる季節になりました。
寒暖差には気をつけて体調を崩さないようご自愛ください。
今回は睡眠の大切さ・重要性についてお話したいと思います。
◎睡眠について
皆さんは普段、どれくらいの睡眠をとっていますか?
睡眠には、1日の活動で蓄積した疲労やストレスから回復させる重要な役割があるため、健康増進・維持には不可欠です。また睡眠時間が極端に短いと、肥満や高血圧、糖尿病などの疾患の発症リスクが高まることも知られています。良い睡眠とは、睡眠の量(睡眠時間)と質(睡眠休養感)が十分に確保されることで可能となり、不適切な睡眠環境、生活習慣及び睡眠障害の発症により損なわれることがあるため、下記の生活習慣を意識して生活してみましょう!
①適度な運動習慣を身につける
日中の身体活動量は睡眠の必要量や質に影響します。また、運動習慣のない人は、睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)が低いこともわかっています。日中に運動することで身体活動量が確保しやすく、寝る直前まで興奮状態が続くことを避けることができるため、運動のタイミングとしておすすめです。夕方や夜の時間帯の運動であっても(目安:就寝2~4時間前まで)睡眠改善に効果があります。運動内容の例としては、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動、ヨガやストレッチ、掃除や洗濯などの家事があげられます。すきま時間を活用して取り組んでみてください。
②しっかり朝食を摂り、就寝前の夜食を控える
朝に日光浴をすることで体内時計の調整に役立つと言われていますが、朝食もまた同様に体内時計の調整に関係します。朝食を欠食すると、体内時計の後退に伴い寝つきが悪くなり、睡眠不足が生じやすくなります。また、朝食の欠食や就寝前の夜食・間食は睡眠休養感の低下にも繋がるため、朝食はしっかり摂り、就寝前の夜食・間食には注意が必要です。
③就寝前にリラックス
スムーズに入眠するためには、リラックスし脳の興奮を鎮めることが大切です。そのため、寝床に就く前の少なくとも1時間前は家事や仕事、勉強に追われずリラックスする時間を作ることがポイントです。また、睡眠時間や就寝時刻に過剰にこだわり、眠気が訪れていない状態で無理に眠ろうとすると、かえって脳の興奮が高まり、寝つきが悪くなることがあります。なかなか寝つけないときは、一度寝床を離れ、寝床以外の静かな場所で眠気が訪れるまで落ち着いた状態で過ごし、眠気が訪れてから寝床に戻ることも1つの手段です。
④規則正しい生活習慣で質の良い睡眠を、日中の活動と夜間の休息・睡眠にメリハリを
質の良い睡眠をとるためには、規則正しい生活を送ることを心がけましょう。夜更かしや不規則な就寝時刻は睡眠不足を招くだけでなく、体内時計の遅れや乱れ、睡眠の質の低下にも影響します。規則正しい生活を維持し、日中は①であげたように明るい環境でできるだけ活動的に過ごし、夜間は③であげたようにやや暗い環境でゆったりとリラックスして過ごし、1日の覚醒と睡眠のリズムにメリハリをつけましょう。
寒暖差には気をつけて体調を崩さないようご自愛ください。
今回は睡眠の大切さ・重要性についてお話したいと思います。
◎睡眠について
皆さんは普段、どれくらいの睡眠をとっていますか?
睡眠には、1日の活動で蓄積した疲労やストレスから回復させる重要な役割があるため、健康増進・維持には不可欠です。また睡眠時間が極端に短いと、肥満や高血圧、糖尿病などの疾患の発症リスクが高まることも知られています。良い睡眠とは、睡眠の量(睡眠時間)と質(睡眠休養感)が十分に確保されることで可能となり、不適切な睡眠環境、生活習慣及び睡眠障害の発症により損なわれることがあるため、下記の生活習慣を意識して生活してみましょう!
①適度な運動習慣を身につける
日中の身体活動量は睡眠の必要量や質に影響します。また、運動習慣のない人は、睡眠休養感(睡眠で休養がとれている感覚)が低いこともわかっています。日中に運動することで身体活動量が確保しやすく、寝る直前まで興奮状態が続くことを避けることができるため、運動のタイミングとしておすすめです。夕方や夜の時間帯の運動であっても(目安:就寝2~4時間前まで)睡眠改善に効果があります。運動内容の例としては、ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動、ヨガやストレッチ、掃除や洗濯などの家事があげられます。すきま時間を活用して取り組んでみてください。
②しっかり朝食を摂り、就寝前の夜食を控える
朝に日光浴をすることで体内時計の調整に役立つと言われていますが、朝食もまた同様に体内時計の調整に関係します。朝食を欠食すると、体内時計の後退に伴い寝つきが悪くなり、睡眠不足が生じやすくなります。また、朝食の欠食や就寝前の夜食・間食は睡眠休養感の低下にも繋がるため、朝食はしっかり摂り、就寝前の夜食・間食には注意が必要です。
③就寝前にリラックス
スムーズに入眠するためには、リラックスし脳の興奮を鎮めることが大切です。そのため、寝床に就く前の少なくとも1時間前は家事や仕事、勉強に追われずリラックスする時間を作ることがポイントです。また、睡眠時間や就寝時刻に過剰にこだわり、眠気が訪れていない状態で無理に眠ろうとすると、かえって脳の興奮が高まり、寝つきが悪くなることがあります。なかなか寝つけないときは、一度寝床を離れ、寝床以外の静かな場所で眠気が訪れるまで落ち着いた状態で過ごし、眠気が訪れてから寝床に戻ることも1つの手段です。
④規則正しい生活習慣で質の良い睡眠を、日中の活動と夜間の休息・睡眠にメリハリを
質の良い睡眠をとるためには、規則正しい生活を送ることを心がけましょう。夜更かしや不規則な就寝時刻は睡眠不足を招くだけでなく、体内時計の遅れや乱れ、睡眠の質の低下にも影響します。規則正しい生活を維持し、日中は①であげたように明るい環境でできるだけ活動的に過ごし、夜間は③であげたようにやや暗い環境でゆったりとリラックスして過ごし、1日の覚醒と睡眠のリズムにメリハリをつけましょう。
(参考文献:厚生労働省 健康づくりのための睡眠ガイド2023)
令和7年2月のひとこと:脂質の検査項目について
みなさん、こんにちは!
バレンタインデーが近づくと街にはチョコレートの陳列が増え、甘いものが好きな方にとっては誘惑の多い時期ですね。
そこで今回はチョコレートにも含まれている気になるもの…
なんとなくわかるようでよくわからない脂質の検査項目についてお伝えしたいと思います。
 当院で検査をしている脂質項目は左表の5項目です。
当院で検査をしている脂質項目は左表の5項目です。
血液検査をされている方には見覚えがある並びかと思います。
(★マークは他の検査項目から計算で出しています。)
【総コレステロール】
コレステロールは悪しきイメージのある方もいるかもしれませんが、体の細胞を包む細胞膜やホルモンなどの材料として欠かせないものです。
【中性脂肪】
脂肪の一種です。食事から摂取したエネルギーは一部中性脂肪として体に蓄えられると皮下脂肪や内臓脂肪となって体温を維持したり、内臓を包んで守っています。また、エネルギーである糖が足りないときには代わりにエネルギー源となります。脂っこいものだけでなく糖も取りすぎると中性脂肪として蓄積されるので要注意です。測定時には食事の影響を受けます。
【HDL-C】
善玉コレステロール
(高比重リポタンパクコレステロール)
体の中で余ったコレステロールを回収して肝臓に集める役割を持っています。
【LDL-C】
悪玉コレステロール
(低比重リポタンパクコレステロール)
肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割を持っています。必要量の7割は体内で合成され残り3割が食事由来です。
★基本的に総コレステロールとHDL-C、中性脂肪の値から算出しますが、中性脂肪の値が高すぎると出すことができません。
【non HDL-C】
(非高比重リポタンパクコレステロール)
★総コレステロールからHDL-Cを差し引いて算出します。
コレステロールや脂肪を抱えているのはHDLやLDLだけではないのです。ほかは分解過程で生じる残り物を発生させます。これらはわずかでも長時間血管内にとどまることで動脈硬化を促進するといわれており、そのため最近はLDL-Cの値だけでなくnon HDL-Cの値が重要視されています。2017年からは動脈硬化性疾患予防ガイドラインにもその診断基準が組み込まれています。
これらの項目の中でHDL-Cだけが余分なコレステロールの回収を行っています。(善玉コレステロール)
つまりHDL-C以外の脂質が多いと血管の中に溜まっていき、血管を詰まらせていく原因になってしまうのです。血中脂質異常はすぐに不調に現れません。また値の変動は食事の影響だけではありません。喫煙や運動不足なども影響します。脂質は身体を作り、バランスを整え、エネルギーになる必要不可欠なものです。ちょうどいいバランスを保てるよう、生活習慣に気をつけていきましょう。
バレンタインデーが近づくと街にはチョコレートの陳列が増え、甘いものが好きな方にとっては誘惑の多い時期ですね。
そこで今回はチョコレートにも含まれている気になるもの…
なんとなくわかるようでよくわからない脂質の検査項目についてお伝えしたいと思います。
 当院で検査をしている脂質項目は左表の5項目です。
当院で検査をしている脂質項目は左表の5項目です。血液検査をされている方には見覚えがある並びかと思います。
(★マークは他の検査項目から計算で出しています。)
【総コレステロール】
コレステロールは悪しきイメージのある方もいるかもしれませんが、体の細胞を包む細胞膜やホルモンなどの材料として欠かせないものです。
【中性脂肪】
脂肪の一種です。食事から摂取したエネルギーは一部中性脂肪として体に蓄えられると皮下脂肪や内臓脂肪となって体温を維持したり、内臓を包んで守っています。また、エネルギーである糖が足りないときには代わりにエネルギー源となります。脂っこいものだけでなく糖も取りすぎると中性脂肪として蓄積されるので要注意です。測定時には食事の影響を受けます。
【HDL-C】

善玉コレステロール
(高比重リポタンパクコレステロール)
体の中で余ったコレステロールを回収して肝臓に集める役割を持っています。
【LDL-C】

悪玉コレステロール
(低比重リポタンパクコレステロール)
肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割を持っています。必要量の7割は体内で合成され残り3割が食事由来です。
★基本的に総コレステロールとHDL-C、中性脂肪の値から算出しますが、中性脂肪の値が高すぎると出すことができません。
【non HDL-C】

(非高比重リポタンパクコレステロール)
★総コレステロールからHDL-Cを差し引いて算出します。
コレステロールや脂肪を抱えているのはHDLやLDLだけではないのです。ほかは分解過程で生じる残り物を発生させます。これらはわずかでも長時間血管内にとどまることで動脈硬化を促進するといわれており、そのため最近はLDL-Cの値だけでなくnon HDL-Cの値が重要視されています。2017年からは動脈硬化性疾患予防ガイドラインにもその診断基準が組み込まれています。
これらの項目の中でHDL-Cだけが余分なコレステロールの回収を行っています。(善玉コレステロール)
つまりHDL-C以外の脂質が多いと血管の中に溜まっていき、血管を詰まらせていく原因になってしまうのです。血中脂質異常はすぐに不調に現れません。また値の変動は食事の影響だけではありません。喫煙や運動不足なども影響します。脂質は身体を作り、バランスを整え、エネルギーになる必要不可欠なものです。ちょうどいいバランスを保てるよう、生活習慣に気をつけていきましょう。
令和7年1月のひとこと:DOCTORS CAFE PLUS
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
今回のひとことは当院併設カフェ、DOCTORS CAFE PLUS ( ドクターズカフェプラス ) の紹介です。
● DOCTORS CAFE PLUSとは
ドクターズカフェプラスは、2018年の当院の増改築とともにできました。
カフェのコンセプトは院長が考案し、調理、販売を含め、カフェの運営は当院の管理栄養士を中心に行っています。
診察や栄養相談で患者さんから「塩分を控えるといってもどのくらいの味付けにすればいいの?」「果物やスイーツはどんなものを食べたらいいの?」などの相談をうけたことをきっかけにできたのがドクターズカフェプラスです。
● DOCTORS CAFE PLUSが提供している「身体によい食」
よく、初めて来られるお客さまには「糖尿病の人しか来られないのかと思っていました」と言われることがありますが、ドクターズカフェプラスは当院に通院中の方だけでなく、一般の方も利用していただけます。

ドクターズカフェプラスでは図のような食事を「身体によい食」としてメニューの考案をしています。
糖尿病の食事療法と聞くと制限食を想像される方が多いと思います。実際栄養相談でお話していてもそのように思っている方は多いと感じます。
糖尿病の食事療法とは、無理な制限食ではなくどんな方にも勧められるようなバランスの良い食事がベースです。
当カフェの食事は塩分を控え、血糖の急激な上昇を起こさないように砂糖は使用せず、質の良い脂質、タンパク質、食物繊維をバランスよく取ることを基本の考え方としており、血圧や脂質、ダイエットなどにも良いメニューとなっています。
もちろん、減塩ながらおいしさにもこだわり、院長や管理栄養士、カフェのスタッフで試作や試食を繰り返してメニューの考案をしています。
● 楽天市場店OPEN!
昨年9月より、楽天市場店をオープンしました。
実店舗では、焼き菓子、プリンやゼリーなどのデザートだけではなく、ランチ、お弁当、お惣菜など幅広く取り揃えていますが、楽天市場店では現在焼き菓子の販売をしています。遠方の方へのギフトなどにもお勧めです。
今後少しずつラインナップを増やしていきたいと考えています。
今回のひとことは当院併設カフェ、DOCTORS CAFE PLUS ( ドクターズカフェプラス ) の紹介です。
● DOCTORS CAFE PLUSとは
ドクターズカフェプラスは、2018年の当院の増改築とともにできました。
カフェのコンセプトは院長が考案し、調理、販売を含め、カフェの運営は当院の管理栄養士を中心に行っています。
診察や栄養相談で患者さんから「塩分を控えるといってもどのくらいの味付けにすればいいの?」「果物やスイーツはどんなものを食べたらいいの?」などの相談をうけたことをきっかけにできたのがドクターズカフェプラスです。
● DOCTORS CAFE PLUSが提供している「身体によい食」
よく、初めて来られるお客さまには「糖尿病の人しか来られないのかと思っていました」と言われることがありますが、ドクターズカフェプラスは当院に通院中の方だけでなく、一般の方も利用していただけます。

ドクターズカフェプラスでは図のような食事を「身体によい食」としてメニューの考案をしています。
糖尿病の食事療法と聞くと制限食を想像される方が多いと思います。実際栄養相談でお話していてもそのように思っている方は多いと感じます。
糖尿病の食事療法とは、無理な制限食ではなくどんな方にも勧められるようなバランスの良い食事がベースです。
当カフェの食事は塩分を控え、血糖の急激な上昇を起こさないように砂糖は使用せず、質の良い脂質、タンパク質、食物繊維をバランスよく取ることを基本の考え方としており、血圧や脂質、ダイエットなどにも良いメニューとなっています。
もちろん、減塩ながらおいしさにもこだわり、院長や管理栄養士、カフェのスタッフで試作や試食を繰り返してメニューの考案をしています。
● 楽天市場店OPEN!
昨年9月より、楽天市場店をオープンしました。
実店舗では、焼き菓子、プリンやゼリーなどのデザートだけではなく、ランチ、お弁当、お惣菜など幅広く取り揃えていますが、楽天市場店では現在焼き菓子の販売をしています。遠方の方へのギフトなどにもお勧めです。
今後少しずつラインナップを増やしていきたいと考えています。
令和6年12月のひとこと:災害時の管理
2024年も残すところ1ヶ月となりました。今年の1月1日には能登半島地震が発生し、その後は
「南海トラフ地震臨時情報」が発表されるなど災害に対する意識が一層高まる年になったことと思います。
大規模災害が起きても、できる限り持病の管理を継続しご自身の身を守れるよう日頃から備えておきたいことについてお話しします。
●お薬手帳を常備しましょう
・東日本大震災の時も、お薬手帳があったことでスムーズかつ適切に医薬品が供給されたという事例が多く報告されています。手帳原本の他に、手帳をコピーした紙や、スマートフォンの中に画像でお薬情報を残しておくのもよいです。
・お薬手帳の中にアレルギーの有無や副作用歴などを記入する欄があるので特記事項を記入しておきましょう。
●内服薬の予備をもちましょう(少なくとも7日~10日分程度)
大規模災害時は救命活動が優先されるため慢性疾患治療薬の供給が遅れたり、物流が滞るために医薬品全体の供給数が少なくなったりする可能性が考えられます。
数日間は手持ちの薬で対処し、その後はお薬手帳を持参し救護所等で相談しましょう。
●こまめな水分摂取を心がけ適度に身体を動かしましょう
・被災後は、飲料水の不足や、トイレが不便になるため水分摂取を我慢してしまうことがあり脱水状態になりやすいです。糖尿病や脂質異常症などのある方はさらに血栓がつくられやすくなり、深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)や脳梗塞・心筋梗塞等の発症リスクが高まります。飲料水の備えと水分摂取を心がけましょう。
・避難生活中でも散歩やラジオ体操をしたり、屈伸運動など足を動かす動作をこまめに行いましょう。
●糖尿病のある方
・クリニックでお渡ししている糖尿病連携手帳を日頃から活用し、お薬手帳とともに常備しましょう。
・インスリン治療中の方は、インスリン製剤・注射針・消毒綿・血糖測定物品の予備をもちましょう。
注射針が不足している時は毎回交換できなくてもやむを得ませんが、他人が使用した針の使い回しは絶対にやめましょう。
1型糖尿病または2型糖尿病でもインスリン分泌が少ない方は、インスリン注射を絶対に中止せず継続してください。
注射針の予備も常に多めにもっておき、インスリンが不足した場合の打ち方については日頃から主治医と相談しておきましょう。
・低血糖への対応のためブドウ糖を常備しましょう。
被災後の不規則な生活環境下では、まずは低血糖を防ぐことを第一と考え、血糖値はいつもより高めでよいと考えましょう。
・被災後の食生活は糖質に偏りがちです。良く噛んでゆっくり食べること、たんぱく質を多く含む食材がある場合はそれを先に食べることを意識し、血糖値の急上昇を防ぎましょう。
「南海トラフ地震臨時情報」が発表されるなど災害に対する意識が一層高まる年になったことと思います。
大規模災害が起きても、できる限り持病の管理を継続しご自身の身を守れるよう日頃から備えておきたいことについてお話しします。
●お薬手帳を常備しましょう
・東日本大震災の時も、お薬手帳があったことでスムーズかつ適切に医薬品が供給されたという事例が多く報告されています。手帳原本の他に、手帳をコピーした紙や、スマートフォンの中に画像でお薬情報を残しておくのもよいです。
・お薬手帳の中にアレルギーの有無や副作用歴などを記入する欄があるので特記事項を記入しておきましょう。
●内服薬の予備をもちましょう(少なくとも7日~10日分程度)
大規模災害時は救命活動が優先されるため慢性疾患治療薬の供給が遅れたり、物流が滞るために医薬品全体の供給数が少なくなったりする可能性が考えられます。
数日間は手持ちの薬で対処し、その後はお薬手帳を持参し救護所等で相談しましょう。
●こまめな水分摂取を心がけ適度に身体を動かしましょう
・被災後は、飲料水の不足や、トイレが不便になるため水分摂取を我慢してしまうことがあり脱水状態になりやすいです。糖尿病や脂質異常症などのある方はさらに血栓がつくられやすくなり、深部静脈血栓症(いわゆるエコノミークラス症候群)や脳梗塞・心筋梗塞等の発症リスクが高まります。飲料水の備えと水分摂取を心がけましょう。
・避難生活中でも散歩やラジオ体操をしたり、屈伸運動など足を動かす動作をこまめに行いましょう。
●糖尿病のある方
・クリニックでお渡ししている糖尿病連携手帳を日頃から活用し、お薬手帳とともに常備しましょう。
・インスリン治療中の方は、インスリン製剤・注射針・消毒綿・血糖測定物品の予備をもちましょう。
注射針が不足している時は毎回交換できなくてもやむを得ませんが、他人が使用した針の使い回しは絶対にやめましょう。
1型糖尿病または2型糖尿病でもインスリン分泌が少ない方は、インスリン注射を絶対に中止せず継続してください。
注射針の予備も常に多めにもっておき、インスリンが不足した場合の打ち方については日頃から主治医と相談しておきましょう。
・低血糖への対応のためブドウ糖を常備しましょう。
被災後の不規則な生活環境下では、まずは低血糖を防ぐことを第一と考え、血糖値はいつもより高めでよいと考えましょう。
・被災後の食生活は糖質に偏りがちです。良く噛んでゆっくり食べること、たんぱく質を多く含む食材がある場合はそれを先に食べることを意識し、血糖値の急上昇を防ぎましょう。
令和6年11月のひとこと:世界糖尿病デー
みなさん、こんにちは!朝夕の寒さにだんだんと冬の訪れを感じるようになりました。季節の変わり目は体調を崩しやすくなるのでぜひ暖かくしてお過ごしください。
皆さんは11月14日が何の日かご存じでしょうか?
正解は「世界糖尿病デー(World Diabetes Day)」です。
2006年12月の国際連合総会で定められてから今年で第18回目となります。11月14日はインスリンを発見したカナダのフレデリック・バンティング博士の誕生日であり、糖尿病治療に画期的な発見に敬意を表し、この日を世界糖尿病デーとして顕彰しています。
世界糖尿病デーは世界に広がる糖尿病の脅威を啓発するために定められました。この日を中心に全世界で糖尿病啓発キャンペーンが行われ、糖尿病の予防や治療継続の重要性について世間に周知する重要な機会となっています。
世界糖尿病デーのキャンペーンには、青い丸をモチーフにした「ブルーサークル」が用いられています。
国際糖尿病連合のシンボルカラーであり、どこまでも続く空を表す「ブルー」と、団結を表す「輪」をデザインし、”Unite for Diabetes”(糖尿病との闘いのため団結せよ)というキャッチフレーズとともに、世界中で糖尿病抑制に向けたキャンペーンを推進しています。このブルーサークルは当院のロゴマークの一部にもなっています。

このキャンペーンの一環で11月14日を中心にその前後約1ヶ月の期間に各地のランドマークや施設が「世界糖尿病デー」のシンボルカラーであるブルーにライトアップされます。去年は静岡県で浜松城がライトアップされたり、東京都庁や大阪城、出雲大社御本殿などもライトアップされました。今年のライトアップ予定は世界糖尿病デー公式ホームページで確認することができます。あそうクリニックでも期間内(11/1~11/30)の日没~23時にかけてブルーライトアップが行われる予定です。
その他にも啓発イベントとして糖尿病に関する一般向けの屋内イベントやセミナー、WEB講演会なども例年開催され、オンラインで参加できるものもあります。これらの開催予定も世界糖尿病デー公式ホームページで確認することができます。
厚生労働省の国民健康・栄養調査(2019年)によると、日本の20歳以上の男性の19.7%、女性の10.8%が糖尿病を強く疑われるとされています。この数値は年々増加傾向で、糖尿病の脅威はより身近なものとなっています。この機会に糖尿病に対する正しい知識を深めるのはいかがでしょうか。

皆さんは11月14日が何の日かご存じでしょうか?
正解は「世界糖尿病デー(World Diabetes Day)」です。
2006年12月の国際連合総会で定められてから今年で第18回目となります。11月14日はインスリンを発見したカナダのフレデリック・バンティング博士の誕生日であり、糖尿病治療に画期的な発見に敬意を表し、この日を世界糖尿病デーとして顕彰しています。
世界糖尿病デーは世界に広がる糖尿病の脅威を啓発するために定められました。この日を中心に全世界で糖尿病啓発キャンペーンが行われ、糖尿病の予防や治療継続の重要性について世間に周知する重要な機会となっています。
世界糖尿病デーのキャンペーンには、青い丸をモチーフにした「ブルーサークル」が用いられています。
国際糖尿病連合のシンボルカラーであり、どこまでも続く空を表す「ブルー」と、団結を表す「輪」をデザインし、”Unite for Diabetes”(糖尿病との闘いのため団結せよ)というキャッチフレーズとともに、世界中で糖尿病抑制に向けたキャンペーンを推進しています。このブルーサークルは当院のロゴマークの一部にもなっています。

このキャンペーンの一環で11月14日を中心にその前後約1ヶ月の期間に各地のランドマークや施設が「世界糖尿病デー」のシンボルカラーであるブルーにライトアップされます。去年は静岡県で浜松城がライトアップされたり、東京都庁や大阪城、出雲大社御本殿などもライトアップされました。今年のライトアップ予定は世界糖尿病デー公式ホームページで確認することができます。あそうクリニックでも期間内(11/1~11/30)の日没~23時にかけてブルーライトアップが行われる予定です。
その他にも啓発イベントとして糖尿病に関する一般向けの屋内イベントやセミナー、WEB講演会なども例年開催され、オンラインで参加できるものもあります。これらの開催予定も世界糖尿病デー公式ホームページで確認することができます。
厚生労働省の国民健康・栄養調査(2019年)によると、日本の20歳以上の男性の19.7%、女性の10.8%が糖尿病を強く疑われるとされています。この数値は年々増加傾向で、糖尿病の脅威はより身近なものとなっています。この機会に糖尿病に対する正しい知識を深めるのはいかがでしょうか。

令和6年10月のひとこと:食事や運動について
みなさんこんにちは!今年も、食欲の秋、運動の秋がやってきました。
数ヶ月前に療養計画書を作成した際に立てた目標を覚えていますか?
計画書見直しの時期になりましたので、今回は目標達成にむけて食事や運動についてお話ししたいと思います。
~血糖高めでも果物を食べたい方へ~
リンゴや梨の皮にはフロリジンが含まれており、尿中に糖を排出させることで血糖値をわずかに低下させる効果が報告されています。
また、皮ごと食べることで、食物繊維も摂取できます。
果物には果糖だけでなく、ブドウ糖やショ糖も含まれており血糖を上昇させます。
さらに、果糖は中性脂肪を上昇させるため、1日の摂取量に注意しましょう。
柿は果物の中でも糖質が高いですが、干し柿にするとさらに高くなり、お菓子の扱いになります!

~血圧高めの方へ減塩のコツ!!!~
「醤油>ポン酢>ソース>ドレッシング>ケチャップ>マヨネーズ>お酢」
これは塩分の多い調味料の順です。減塩のコツとして、使用する調味料を替えてみましょう!
・お寿司に醤油をつける→ドレッシングに変える
和風ドレッシングはあっさりして意外と美味しいです。
・冷や奴に醤油をつける→ポン酢に変える
・サラダにドレッシングをつける→マヨネーズに変える
また調味料は小皿に出してつけることでかけ過ぎの注意ができます。
いろんな組み合わせを考えて楽しく減塩してみましょう!
~簡単にできるながら運動をご紹介~
★首の体操
・首を「前」「後ろ」「右を向く」「左を向く」と動かしてみましょう!肩こり予防にもなります。
★座ったまま血行改善
・イスに座りかかとを床につけ、つま先を上げ、指先を縮めたり、
大きく開いたり繰り返してみましょう。
→繰り返すと足首が引き締まり、ふくらはぎの血行がよくなりむくみ防止になります。
常に姿勢を意識するだけでも、筋力を使うため筋トレになります。
★外出先でもながら運動
・移動の際は背筋を伸ばし、いつもより大股で歩いてみましょう。
★イスを使ったスクワット
・肩幅に両足を開き、腕を前に伸ばし身体を前傾させながらゆっくり立ち上がり、
全身を伸ばす、その後ゆっくり腰を下ろし元の姿勢へ。
→イスを使用することで膝への負担を軽減させスクワットができます。
体調の変化に注意しつつ、運動は無理のない範囲で行ってみて下さい。水分補給も忘れずに!!
最近の食事・運動療法はどうでしょうか?再度食生活を見直し目標達成を目指しましょう。
また、栄養相談希望の際は診察時に医師へお申し出ください。
数ヶ月前に療養計画書を作成した際に立てた目標を覚えていますか?
計画書見直しの時期になりましたので、今回は目標達成にむけて食事や運動についてお話ししたいと思います。
~血糖高めでも果物を食べたい方へ~
リンゴや梨の皮にはフロリジンが含まれており、尿中に糖を排出させることで血糖値をわずかに低下させる効果が報告されています。
また、皮ごと食べることで、食物繊維も摂取できます。
果物には果糖だけでなく、ブドウ糖やショ糖も含まれており血糖を上昇させます。
さらに、果糖は中性脂肪を上昇させるため、1日の摂取量に注意しましょう。
柿は果物の中でも糖質が高いですが、干し柿にするとさらに高くなり、お菓子の扱いになります!

~血圧高めの方へ減塩のコツ!!!~
「醤油>ポン酢>ソース>ドレッシング>ケチャップ>マヨネーズ>お酢」
これは塩分の多い調味料の順です。減塩のコツとして、使用する調味料を替えてみましょう!
・お寿司に醤油をつける→ドレッシングに変える
和風ドレッシングはあっさりして意外と美味しいです。
・冷や奴に醤油をつける→ポン酢に変える
・サラダにドレッシングをつける→マヨネーズに変える
また調味料は小皿に出してつけることでかけ過ぎの注意ができます。
いろんな組み合わせを考えて楽しく減塩してみましょう!
~簡単にできるながら運動をご紹介~
★首の体操
・首を「前」「後ろ」「右を向く」「左を向く」と動かしてみましょう!肩こり予防にもなります。
★座ったまま血行改善
・イスに座りかかとを床につけ、つま先を上げ、指先を縮めたり、
大きく開いたり繰り返してみましょう。
→繰り返すと足首が引き締まり、ふくらはぎの血行がよくなりむくみ防止になります。
常に姿勢を意識するだけでも、筋力を使うため筋トレになります。
★外出先でもながら運動
・移動の際は背筋を伸ばし、いつもより大股で歩いてみましょう。
★イスを使ったスクワット
・肩幅に両足を開き、腕を前に伸ばし身体を前傾させながらゆっくり立ち上がり、
全身を伸ばす、その後ゆっくり腰を下ろし元の姿勢へ。
→イスを使用することで膝への負担を軽減させスクワットができます。
体調の変化に注意しつつ、運動は無理のない範囲で行ってみて下さい。水分補給も忘れずに!!
最近の食事・運動療法はどうでしょうか?再度食生活を見直し目標達成を目指しましょう。
また、栄養相談希望の際は診察時に医師へお申し出ください。
令和6年9月のひとこと:夏の疲れを残さないための食事のポイント
みなさんこんにちは!厳しい残暑が続いていますが、体調はいかがでしょうか。
夏の疲れが溜まっていませんか?これからの季節を楽しむためにも、日頃の食生活を振り返り、早めの対処をして残暑を乗り切りましょう。
今回は夏の疲れを残さないための食事のポイントをお話します。
●夏バテの原因
夏場の冷房による室内と屋外の温度差や、冷たい物を食べたり飲んだりすることで内蔵が冷えることで自律神経が乱れ血行不良となります。それにより食欲不振や消化機能の低下、また夏の暑さによる睡眠不足が重なり、慢性的に疲労が溜まる…
これが「夏バテ」の原因と言われています。
●疲労回復の食事のポイント
①主食+主菜+副菜のバランスの良い食事を意識しましょう
夏場はさっぱりと麺類を食べる機会も多いと思います。麺+薬味だけにならないよう冷やし中華のような単品でもたんぱく質と野菜が乗っているようなメニューがおすすめです。
②疲労回復効果のある栄養素をとりましょう
・ビタミンB1…………豚肉、うなぎ、カツオ、玄米、ごまなど
糖質を体内でエネルギーに変えるために不可欠です。また疲労や身体のだるさ、食欲不振の予防にも役立ちます。
・ビタミンC…………パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ、レモンなど
細胞の酸化を防ぎ、身体の免疫力を高める働きがあります。
ストレスに対抗するホルモンの合成を促す働きもあります。
紫外線や睡眠不足、疲労など多くのストレスにさらされる夏はビタミンCの消費量が増えるため不足しないよう補給を心掛けてください。
・ミネラル……………海藻、果物、緑黄色野菜など
汗と共にミネラルが失われてしまいます。
ミネラルが不足すると脱力感、筋力低下、食欲不振に繋がるためしっかりと補給しましょう。
・たんぱく質…………肉、魚、卵、大豆製品など
筋肉や血液など体をつくるために大切な栄養素です。
筋肉疲労を解消させたり、体の持久力をアップさせたりする働きがあります。
③こまめな水分補給を心掛けましょう
喉の渇きを感じる前に定期的に飲むようにしましょう。
甘い飲み物は糖分の分解にビタミンB1を多量に消費するため疲労感を招きやすくなります。
水やミネラルが含まれる麦茶での水分補給がおすすめです。
食事の他にも身体を冷やしすぎないこと、十分な睡眠をとることも大切です。
夏の疲れを引きずらないためにも、まずはできることから始めましょう!
夏の疲れが溜まっていませんか?これからの季節を楽しむためにも、日頃の食生活を振り返り、早めの対処をして残暑を乗り切りましょう。
今回は夏の疲れを残さないための食事のポイントをお話します。
●夏バテの原因
夏場の冷房による室内と屋外の温度差や、冷たい物を食べたり飲んだりすることで内蔵が冷えることで自律神経が乱れ血行不良となります。それにより食欲不振や消化機能の低下、また夏の暑さによる睡眠不足が重なり、慢性的に疲労が溜まる…
これが「夏バテ」の原因と言われています。
●疲労回復の食事のポイント
①主食+主菜+副菜のバランスの良い食事を意識しましょう
夏場はさっぱりと麺類を食べる機会も多いと思います。麺+薬味だけにならないよう冷やし中華のような単品でもたんぱく質と野菜が乗っているようなメニューがおすすめです。
②疲労回復効果のある栄養素をとりましょう
・ビタミンB1…………豚肉、うなぎ、カツオ、玄米、ごまなど

糖質を体内でエネルギーに変えるために不可欠です。また疲労や身体のだるさ、食欲不振の予防にも役立ちます。
・ビタミンC…………パプリカ、ブロッコリー、キウイフルーツ、レモンなど
細胞の酸化を防ぎ、身体の免疫力を高める働きがあります。
ストレスに対抗するホルモンの合成を促す働きもあります。
紫外線や睡眠不足、疲労など多くのストレスにさらされる夏はビタミンCの消費量が増えるため不足しないよう補給を心掛けてください。
・ミネラル……………海藻、果物、緑黄色野菜など
汗と共にミネラルが失われてしまいます。
ミネラルが不足すると脱力感、筋力低下、食欲不振に繋がるためしっかりと補給しましょう。
・たんぱく質…………肉、魚、卵、大豆製品など
筋肉や血液など体をつくるために大切な栄養素です。
筋肉疲労を解消させたり、体の持久力をアップさせたりする働きがあります。
③こまめな水分補給を心掛けましょう
喉の渇きを感じる前に定期的に飲むようにしましょう。
甘い飲み物は糖分の分解にビタミンB1を多量に消費するため疲労感を招きやすくなります。
水やミネラルが含まれる麦茶での水分補給がおすすめです。
食事の他にも身体を冷やしすぎないこと、十分な睡眠をとることも大切です。
夏の疲れを引きずらないためにも、まずはできることから始めましょう!
令和6年8月のひとこと:オーラルフレイル
みなさん、「健康長寿の為の三つの柱」をご存じでしょうか?
① 歯と口の機能を維持しておいしく食べる
② 運動を十分にして身体活動を保つ
③ 趣味やボランティア活動などを生かしながら社会とつながる
と言われています。年齢を重ねるとこれらの柱が脆弱になり、そのままでは
「フレイル(高齢による衰弱)」に陥ります。
「オーラルフレイル」を知っていますか?
オーラルは「口」、フレイルは「虚弱」を意味します。
かたい物が食べづらくなったり、滑舌が悪くなったり、加齢に伴うお口の衰えが栄養不足や、気持ちの落ち込みなどを引き起こします。
お口の健康は、身体と心の健康にまでつながっています。
また、糖尿病や肥満の方は、咀嚼機能や舌・口の運動機能が衰えやすいと言われています。


オーラルフレイルになると、歯周病から糖尿病数値の悪化なども引き起こします。
いつまでも、健口。すなわち歯と口を健やかに保つことは、糖尿病治療にも大きく関係しますので、年に1回の歯科検診をお勧めします。
その際は、糖尿病連携手帳を持参し受診してみてください。
① 歯と口の機能を維持しておいしく食べる
② 運動を十分にして身体活動を保つ
③ 趣味やボランティア活動などを生かしながら社会とつながる
と言われています。年齢を重ねるとこれらの柱が脆弱になり、そのままでは
「フレイル(高齢による衰弱)」に陥ります。
「オーラルフレイル」を知っていますか?
オーラルは「口」、フレイルは「虚弱」を意味します。
かたい物が食べづらくなったり、滑舌が悪くなったり、加齢に伴うお口の衰えが栄養不足や、気持ちの落ち込みなどを引き起こします。
お口の健康は、身体と心の健康にまでつながっています。
また、糖尿病や肥満の方は、咀嚼機能や舌・口の運動機能が衰えやすいと言われています。


合計点数が3点以上、または歯や口に気になる変化がある場合には、
歯科への受診や検診をお勧めします。
歯科への受診や検診をお勧めします。
オーラルフレイルになると、歯周病から糖尿病数値の悪化なども引き起こします。
いつまでも、健口。すなわち歯と口を健やかに保つことは、糖尿病治療にも大きく関係しますので、年に1回の歯科検診をお勧めします。
その際は、糖尿病連携手帳を持参し受診してみてください。
令和6年7月のひとこと:動脈硬化と検査
みなさんこんにちは!蝉の声が賑やかな季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
今回は動脈硬化と動脈硬化検査についてお話していきたいと思います。
動脈硬化とは
動脈硬化とは、動脈の血管壁が弾力を失い、硬くなり厚くなって、脆くなる病態です。
動脈硬化は言い換えると血管の「老化」のことで、誰しも多かれ少なかれ、年齢とともに起こってきますが、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの動脈硬化の危険因子を持っている方は、特に進行しやすくなります。
動脈硬化の進行した方は、同じ年齢の方に比べて、血管も年をとって脆くなっており、それだけ血管が詰まったり、破れたりする脳血管・心血管イベントのリスクが高くなります。
アテローム性動脈硬化
動脈硬化はいくつか種類がありますが、アテローム性動脈硬化は最も重要で最もよく見られる動脈硬化です。
通常動脈は心臓から血液を全身に送り届けるため強い弾力性を持っていますが、動脈硬化の危険因子により血管が脆くなってしまうと血管にプラークと呼ばれる余分なコレステロールの塊が発生します。
プラークが進行して大きくなると血管内壁が狭くなってしまい、血流の流れが悪くなったり、血管が硬くなっていきます。
さらに進行すると血栓と呼ばれる血液の塊が発生し、血管が詰まってしまったり、一部が剥がれて脳まで流れてしまうこともあります。

動脈硬化検査
院内では動脈硬化の検査としてABI・CAVI検査と頸動脈エコーを実施しています。
ABI・CAVI検査では患者さんに仰向けに寝てもらい、両上腕と両足首に血圧測定の時に巻くカフと胸元に心音マイクをつけて検査します。ABI検査では動脈硬化が進行して発生した血栓によって足の血管が狭くなったり詰まったりしていないか両上腕と両足首の血圧を比較して検査しています。
CAVI検査では大動脈を含む心臓から足首までの血管の硬さを評価したり、同じ性別、同年齢の健康な方のCAVI検査の平均値を比べることで血管年齢も評価しています。
頸動脈エコーは首に超音波を当てて頸動脈の画像から頸動脈の血管壁の厚さや血管内部の状態を確認しています。
この検査ではプラークの厚さや動脈が狭くなっていないか評価しており、頸動脈は心臓から脳などの全身と繋がっているため、全身の動脈硬化度を示すよい指標となります。
ABI・CAVI検査と頸動脈
エコーはその場で検査結果が出るので当日に医師の説明を受けることができます。
動脈硬化の危険因子を持っている方や検査について興味がある方はお気軽にスタッフに声をかけてください。
これからますます厳しい暑さになりますのでお体に気を付けてお過ごしください。
今回は動脈硬化と動脈硬化検査についてお話していきたいと思います。
動脈硬化とは
動脈硬化とは、動脈の血管壁が弾力を失い、硬くなり厚くなって、脆くなる病態です。
動脈硬化は言い換えると血管の「老化」のことで、誰しも多かれ少なかれ、年齢とともに起こってきますが、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの動脈硬化の危険因子を持っている方は、特に進行しやすくなります。
動脈硬化の進行した方は、同じ年齢の方に比べて、血管も年をとって脆くなっており、それだけ血管が詰まったり、破れたりする脳血管・心血管イベントのリスクが高くなります。
アテローム性動脈硬化
動脈硬化はいくつか種類がありますが、アテローム性動脈硬化は最も重要で最もよく見られる動脈硬化です。
通常動脈は心臓から血液を全身に送り届けるため強い弾力性を持っていますが、動脈硬化の危険因子により血管が脆くなってしまうと血管にプラークと呼ばれる余分なコレステロールの塊が発生します。
プラークが進行して大きくなると血管内壁が狭くなってしまい、血流の流れが悪くなったり、血管が硬くなっていきます。
さらに進行すると血栓と呼ばれる血液の塊が発生し、血管が詰まってしまったり、一部が剥がれて脳まで流れてしまうこともあります。

動脈硬化検査
院内では動脈硬化の検査としてABI・CAVI検査と頸動脈エコーを実施しています。
ABI・CAVI検査では患者さんに仰向けに寝てもらい、両上腕と両足首に血圧測定の時に巻くカフと胸元に心音マイクをつけて検査します。ABI検査では動脈硬化が進行して発生した血栓によって足の血管が狭くなったり詰まったりしていないか両上腕と両足首の血圧を比較して検査しています。
CAVI検査では大動脈を含む心臓から足首までの血管の硬さを評価したり、同じ性別、同年齢の健康な方のCAVI検査の平均値を比べることで血管年齢も評価しています。
頸動脈エコーは首に超音波を当てて頸動脈の画像から頸動脈の血管壁の厚さや血管内部の状態を確認しています。
この検査ではプラークの厚さや動脈が狭くなっていないか評価しており、頸動脈は心臓から脳などの全身と繋がっているため、全身の動脈硬化度を示すよい指標となります。
ABI・CAVI検査と頸動脈
エコーはその場で検査結果が出るので当日に医師の説明を受けることができます。
動脈硬化の危険因子を持っている方や検査について興味がある方はお気軽にスタッフに声をかけてください。
これからますます厳しい暑さになりますのでお体に気を付けてお過ごしください。